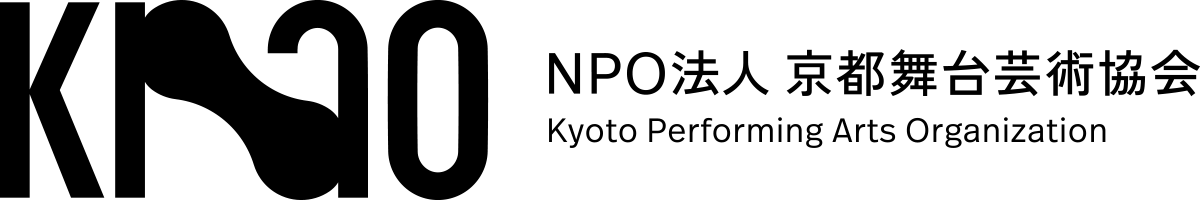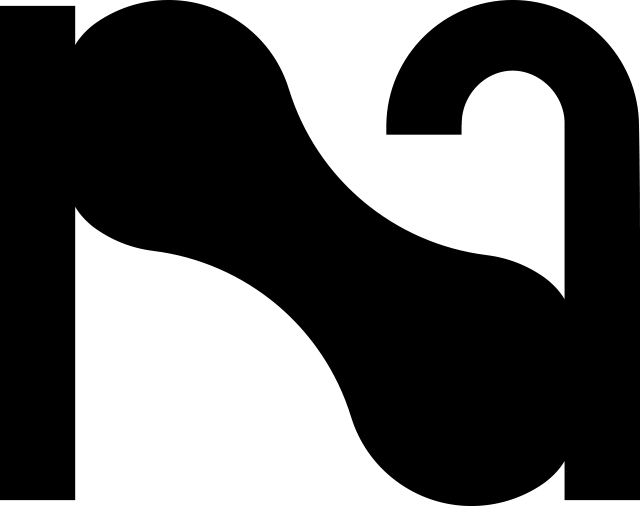※「四半期だべりば」とは…京都舞台芸術協会がおよそ四半期ごとに協会の活動や舞台芸術関連の出来事をざっくばらんにおしゃべりする企画です。
この記事は2025年8月31日に収録された「四半期だべりば」の内容をAIがブログ風にレポートしたものです。
「四半期だべりば」(2025年8月31日収録分)本編は下記リンクからSpotifyでご視聴可能です。
https://open.spotify.com/episode/36VMIuuobDdzUNkUPP71GL?si=qaSm78P6Q_aHA71DGK9tDA
よろしければご視聴とともにコメントでご意見・ご感想をお聞かせください!
演劇の「常識」をひっくり返す3つの視点:
京都のアーティストたちの対話から見えた舞台芸術のリアル
舞台芸術と聞くと、多くの人が華やかなスポットライト、一体感に満ちた劇団、そして完成された作品が上演される荘厳な劇場を思い浮かべるかもしれない。しかし、その創造の現場では、私たちの想像とは少し違う、リアルな葛藤や発見が日々生まれている。もし、アーティストたちの楽屋裏での率直な会話を覗き見ることができたら、私たちは何を知ることができるのだろうか。
この記事では、先日行われたNPO法人京都舞台芸術協会のラウンドテーブルディスカッションの記録をもとに、普段は聞くことのできないアーティストたちの本音を紐解いていく。集ったのは、演出家、舞台美術家、制作者といった、異なる立場から舞台芸術に関わる人々。彼らの言葉の端々から見えてきたのは、私たちが抱く演劇のイメージを鮮やかに裏切る、3つの示唆に富んだ「驚くべき視点」だった。これは、舞台芸術の現在地を知るための、貴重なインサイドレポートである。
——————————————————————————–
本文:アーティストたちの対話から見えた3つの視点
1. 劇団の存続は「ほぼ奇跡」であるという現実
「劇団」という言葉には、固い結束で結ばれた創作集団というロマンチックな響きがある。しかし、アーティストたちの対話は、その存続がいかに困難なバランスの上に成り立つ「奇跡的な」営みであるかを浮き彫りにする。
30周年を迎えた劇団衛星や、劇団員の見事な連携が光ったという不労者の公演を振り返る中で、彼らは劇団の看板を背負って舞台に立つことの力強さや、メンバー間の深い信頼関係が作品の質に直結することを語る。演出家が、いざという時に「背中を預けられる存在」として劇団員を頼り、俳優がそれに応える。この関係性こそが、プロデュース公演にはない劇団ならではの魅力だろう。
しかしその一方で、ある人物の言葉が、その維持がいかに難しいかを突きつける。自身も「一度劇団という形態を諦めた立場」だと語る演出家の神田真直氏だ。
維持されてること自体がもうほぼ奇跡みたいなものだという風に思う
特定の稽古場所も、安定した制度も整備されていない中で、単なる「仲良し」というだけではない、創作におけるシビアな信頼関係を、複数の人間が長期間にわたって維持し続ける。それは並大抵のことではない。
だからこそ、劇団は存続のために絶え間ない努力を続けている。劇団三毛猫座を率いる演出家のneco氏は、メンバーが入れ替わる「新陳代謝」が繰り返された結果、組織が活性化された面もあったと語る。また、カンパニー「ソノノチ」の制作者である渡邉裕史(べってぃ)氏は、合宿や勉強会を内部で開き、意識的に「共有地を増やす」時間を設けているという。劇団とは、情熱だけで成り立つものではなく、極めて繊細で知的な努力によって支えられている共同体なのだ。
2. 「劇場から出たい」アーティストと「劇場に帰りたい」アーティストの対立
この劇団という「奇跡」を維持するための苦闘は、自ずと「では、その芸術はどこで上演されるべきなのか?」という根源的な問いへとつながっていく。そしてこの「場所」を巡る考え方も、アーティストたちの間で決して一枚岩ではない。むしろそこには、それぞれのキャリアに根差した、興味深い視点の対立が存在した。
一方は、積極的に「劇場から出たい」と考える舞台美術家の竹内良亮氏だ。彼は近年、ホテルや廃工場といった、劇場以外の空間での創作に興味が移っていると語る。その場所がもともと持っている歴史や「背景を活かして」作品を立ち上げること。あるいは、たとえブラックボックス型の劇場であっても、その場所性をあえて剥き出しにすることに関心があるという。
袖幕とか全部いらんやんとか思っちゃってる。
彼のこの言葉は、整えられた「劇場」という装置そのものを解体し、空間とフラットに向き合いたいという、美学的な進化の表れだ。
対照的なのが、「ちゃんとした劇場でやりたい」と強く願う神田氏の視点である。大学卒業後、あるいはコロナ禍において、プロフェッショナルな創作の場である劇場から「1回追い出されるわけですよ」と彼は語る。劇場ではない場所での創作を「妥協でやってるみたいな感覚が実は強くて」と吐露する彼の言葉は、専門的な設備と環境が整った「劇場」という空間への切望であり、それは芸術的志向というよりも、プロとしての活動基盤を求める切実な叫びに近い。
この「劇場から出たい」竹内氏と、「劇場に帰りたい」神田氏。二人の視点の違いは、単なる好みの問題ではない。それは、演劇人としての「育ち」や経験の違いから生まれる、芸術的哲学とプロとしての生存戦略の対話なのだ。「どこで上演するか」という選択は、現代の舞台芸術における極めて重要な創作上の問いとなっている。
3. 「カフェでもある劇場」:私たちの生活に足りないもの
対話の終盤、この場所を巡る問いに一つの光を当てるかのように、神田氏がベルリンで体験した劇場の姿が語られた。それは、日本の劇場のあり方を根本から問い直す、鮮やかな事例だった。
ベルリンの劇場は、単に演劇を上演するだけの場所ではない。そこにはカフェが併設されており、観劇の予定がない人々も日常的に立ち寄り、お茶を飲んだり会話をしたりして時間を過ごす「たまり場」としての機能を持っているという。
生活の中に劇場があるな、と感じさせてくれる場所ってすごくいいなって思ってて
この言葉が示すのは、劇場が特別な「ハレ」の空間であるだけでなく、人々の日常に溶け込んだ「ケ」の空間でもあるという事実だ。
翻って日本の劇場はどうだろうか。公演が終われば「近隣の皆様のご迷惑になりますので、お早めにお帰りください」というアナウンスが流れ、観客はすぐに追い出されてしまう。そこには、余韻に浸ったり、感想を語り合ったりする時間も場所もほとんどない。
ベルリンの事例は、劇場が単なる「上演施設」ではなく、人々が集い、交流する「共有空間(サードプレイス)」になる可能性を示唆している。もし近所の劇場が、いつでも気軽に立ち寄れるカフェのような場所であったなら。それは、劇団の活動に安定した社会的基盤を与え(第1の視点)、劇場の中と外を巡る対立を乗り越える新しい価値を生み出す(第2の視点)きっかけになるかもしれない。
——————————————————————————–
結論部:まとめ
今回、京都のアーティストたちの対話から見えてきたのは、「劇団存続の奇跡」「上演場所を巡る葛藤」、そして「劇場の社会的な役割」という3つの視点だった。これらは、舞台の上で何が表現されるかという「作品の内容」だけでなく、それを生み出し、支える「仕組み」や「考え方」そのものが、現代の舞台芸術における重要なテーマであることを示している。
彼らの言葉は、演劇が一部の専門家や愛好家だけのものではなく、私たちの生活や社会と地続きにある文化であることを改めて教えてくれる。
最後に、この記事を読んでくださったあなたに問いかけたい。私たちが住む街には、どのような劇場があれば、毎日はもっと豊かになるだろうか?
以上、AIによる「四半期だべりば」視聴ブログ風レポートでした!