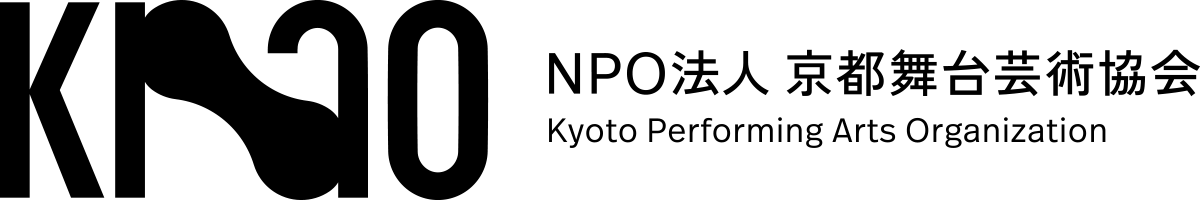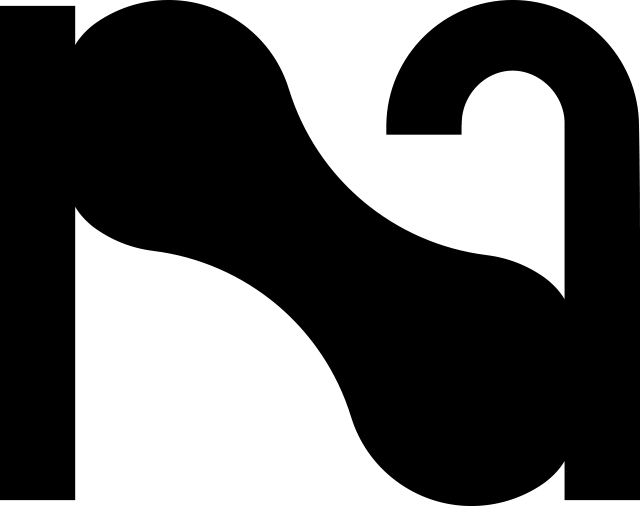年間50〜60本の舞台を観ているのに、ほとんど感想らしきものを書いたことがない。仕事で講評を書くことはあるけど、それはやはり仕事だし、その舞台を観た人が読むことが前提になっているので特に抵抗はない。しかしブログに感想を書くとなると、その舞台を観ていない人には興味が無いだろう、とか、真意が伝わらなかったら嫌だなあ、などと逡巡しているうちにタイミングを逃してしまう。
今回にしたって観劇したのは10日ほど前のことであって、しっかりタイミングは逃しているのだけれど、最近の私の思考に響くものがあって何だかモヤモヤが続くので、この際吐き出してしまおうと思った次第だ。個人のブログの特性上、作品よりも私の思考によることは前もって了承頂きたい。
井上荒野さんの小説「雉猫心中」を基にして構成された「私はもう帰らない。」。ほら、もうこれだけで期待と不安が混ざり合いどくどく脈打つ。 もちろん天秤は不安のほうに大きく傾いている。文学を演劇で取り扱うのは本当に大変なのだ。朗読ならいい。しかしこれは演劇。小説の肝である情景や心情の描写を割愛して、セリフで構成しなくてはならないのだから。私は昨年、AAFリージョナルシアターで芥川龍之介を舞台化するプロジェクトを企画して、演劇が文学に挑む恐ろしさを味わった。だってテキストという媒体で完成しているものを敢えて創り直すということは、原作の完成度や芸術性に依ることではなく、その圧倒的存在の前に丸裸で晒され、まさに対峙するということだからだ。芥川は紛れも無く巨人だったが、井上荒野さんだってれっきとした直木賞作家。大層な巨木である。拮抗するには相当な胆力が必要であろう。小説の面白さを伝えようと作品創りを進めていくと、味方だと思っていた小説はその牙を剥いて襲い掛かってくる。力を貸してくれるどころか創り手の喉元に鋭利な刃物を突きつけてくる、「お前はやれるのか?」と。ただただ創り手の作家性が、芸術性が試されるのだ。それは本当に当たり前のことで、何かに題材を借りようが借りまいが作品を創るということはシンプルに「そういうこと」でしかない。そんな当たり前のことを「巨人」を鏡にして思い知らされるのだ、演劇が文学を扱うと。そして、その怖さを知らない人間の作品は途方もなくつまらない。それはもう、本当につまらない。
実に後味が悪い。
観劇後の率直な感想となるとまあそういうことになるのだけれど、このネガティブな表現の意味するところはお芝居がある程度機能していたことを意味している。なんたって文学の魅力なんてものは後味の悪さに代表されるモヤモヤなんであって、すっきり爽快なものなんて、いやそれはそれで価値があるけれど、少なくとも井上荒野さんの作風ではない。純文学のあらすじなんてあってないようなもので、その価値は、その他愛のない人物の行動や思考を文字を駆使して如何に滲ませるか、何を炙り出すか、ということになっているんであって、「私はもう帰らない。」はそれを見事に舞台上に引きずり出していた。
小説では情景や心情が文字で表現されているけれど、演劇において俳優が舞台上でそれを表現するには沈黙を如何にうまく使うかということになっていて、いちいちその心情をト書きでも読むように語るならそれはもう完全な敗北を意味していて、早い話が小説読んだほうがいい。 しかし「私はもう帰らない。」ではたくさんの情報が詰まった饒舌な沈黙が空間を支配していて、真っ向から勝負したな!という感想を持つ。小説を、セリフだけ抜き出して表現しようとすると、それはほとんど沈黙になるんであって、真っ向勝負とはそういう意味だ。確かに朗読感もあるにはあったが、ある程度筋を説明する上では仕方がなかったのかなとお目こぼし。そうはいっても、俳優の動きを止めて説明ゼリフを言わせその終わりは次のシーンへとシームレスに繋がっている、とか、棒読みに近いニュートラルな発話をすることで逆に文字を人間の生々しさへと転化させている、など演出が施されていて、ただ舞台上で説明的に小説の一部を読んだという敗北感は薄めてあった。その辺の手つきは見事であった。
猫の扱いが上手でなかったことは言葉に頼らざるをえない以上やむを得ないが、ただ一点、その猫の存在がペルソナの変容に一役買っていたことは評価できる。度々出てくる猫の描写は、不倫をする二人にとって相手との関わりのようでもあり、ともすれば自分を俯瞰しているようでもあり、それは舞台上で不倫相手の女性と妻とを行ったり来たりする女優のペルソナにダイナミズムを与えていた。私は「俳優とは他人の人生を生きることだ」とか「俳優とは他人になりきることだ」とかいった類の俳優論にはほとほと反吐が出る。教育の場で転用される演劇では、ペルソナを被せることで自由になれるよう促すという手は有効だが、やはりそれは俳優の職能の一部にすぎないし、突き詰めると「何者にもなれない自分を受け入れる」ことでしかない。その「自分でしかないというジレンマ」こそが俳優を舞台に立たせるんであって、まあそれもひとつの俳優の職能に過ぎないと言われればそれまでだ。ただここでひとつ興味深いのは、表現の自由を促す手段として別のペルソナを被せる、つまり演じればいいんだ、「それは君じゃないんだ」という方法がある一方で、何も演じなくていいんだ、「自分でいいんだよ」と言ってあげることが非常な助けになることがある。この相反する二つが同じ効能を持ち屹立していることは、やはりこの正反対の二つは根源的に同じことを意味しているということであって、それがどういうことなのかは俳優として探る価値があると思っている。少し脱線したが、猫の効果もあって、舞台上で女優が不倫相手だったり妻だったり、どっちか分からず二重のペルソナを被っているように見えてみたり、またその実その女優のドキュメンタリズムにも感じられたり。そんな歪みが生まれたのは意図的か否かは分からないが 、この作品の一番の功績であって、発話の技術や身体性も越えた、俳優の存在論へ投じた一石ではなかろうか。
平塚らいてふは女性の権利を主張したが、それは男性に取って代わろうというものではなかった。またネルソン・マンデラはアパルトヘイトという政策と闘ったが、白人に取って代わろうというものではなかった。共存を目指して闘っていた。嗚呼、風呂敷を広げすぎない方がいい・・・ とにかく、俳優は相反する事象や思想の共存の先に見えてくるに違いない。演じることと演じないことが同義であることが私にそう語りかけてくる。